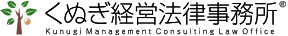遺留分は、請求できる期間に制限があるなど、その行使方法や評価方法などが複雑です。
そのため、適切な法律知識を持って適切に対処しなければなりません。
遺留分問題とは?
相続では、被相続人の意思が尊重されますので、全ての遺産を特定の相続人に相続させる遺言がある場合など、特定の者だけが優遇されているというケースが、多く見受けられます。
しかし、これでは、残された他の相続人の生活の基盤が失われる可能性があります。
そのようなことがないよう、相続人に最低限の財産を法律上保証した制度が「遺留分」です。
遺留分の割合は、次のとおり法律上定められています。
・配偶者
・直系卑属のどちらか一方でもいる場合・・遺産の2分の1が遺留分
・直系尊属だけの場合・・遺産の3分の1が遺留分
・兄弟姉妹・・遺留分なし
また、遺留分算定の基礎財産は、次のとおり計算すると定められています。
「相続開始時にあった財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務の全額」
以下、遺留分が、具体的にどのような場面で問題となるのか、具体例を交えて、ご説明致します。
遺留分に関して問題となるケース
特定の者が全ての遺産を相続するという遺言がある。
- 具体例
遺留分が問題となる最も代表的な例は、被相続人が全ての遺産を、特定の相続人や第三者に譲り渡すという遺言を残しているケースです。
特に、このような遺言に加え、遺産の内容を正確に把握できていない場合、遺産の取得自体を諦めてしまう方が多くいらっしゃいます。
-
対処方法
遺産の内容が正確に分からなくとも、遺留分の請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しなければ時効により消滅してしまいます。
そのため、遺産の内容が正確に分からなくとも、まずは内容証明郵便を利用して、遺留分減殺請求権を行使し、時効完成を阻止することが必須ですから、お早目にご相談いただくことをお勧め致します。
その後、任意での交渉では解決できない場合、遺留分減殺請求を求める調停もしくは訴訟により解決することになります。
被相続人から財産の大部分贈与された相続人でない第三者がいる。
- 具体例
被相続人が、生前に、財産の大部分を第三者(相続人以外)に贈与したことで、遺産が全くないというケースが考えられます。
このような贈与があると、相続人の生活の基盤が失われてしまうこともありますが、そのようなことがあってはなりません。
-
対処方法
贈与を受けた第三者に対して、遺留分減殺請求権を行使することができないか、検討することになります。
遺留分の基礎財産には、相続開始前の1年間になされた贈与も含まれますから、もし、贈与の時期が被相続人の死亡から1年以内になされたものであれば、遺留分減殺請求権を行使することが可能です。
また、相続開始前の1年より前になされた贈与であっても、「遺留分権利者に損害を与えることを知って」なされた贈与であれば、遺留分の基礎財産に含まれることになります。
「遺留分権利者に損害を与えることを知って」なされたかどうかは個別の事案によりますが、いずれにしても、1年より前の贈与だからといって遺留分減殺請求権の行使を諦めるべきではありません。
被相続人から多額の贈与を受けていた相続人がいる。
- 具体例
相続人の一人が、被相続人の生前に、被相続人から多額の財産の贈与を受けていたことで、分配すべき遺産がなくなり、相続人間で不公平が生じている、というケースが考えられます。
もし、残された遺産があれば、特別受益の主張等することで遺産の配分を調整することも可能ですが、遺産がないことから、それができません。
-
対処方法
このようなケースの事例においては、贈与を受けた相続人に対して、遺留分減殺請求権を行使することができないか、検討することになります。
相続人に対して贈与がなされ、それが「特別受益」に該当する場合には、特段の事情のない限り、遺留分の算定対象となります(最高裁判所平成10年3月24日付判決)。
なお、この贈与は、相続開始より相当前になされたものでも、遺留分の算定対象になります。
ただし、民法(相続法)の改正により、相続開始よりも相当前に贈与を受けた受贈者の地位の安定性を確保する必要から、遺留分算定の基礎財産に組み入れることのできる贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限られることになりました。また、生前贈与財産は、贈与時の価額ではなく、相続時の価額で評価することになります。
被相続人から著しく安く不動産を購入した相続人がいる。
- 具体例
被相続人から、不動産を極めて安い価額(贈与同然の価額)で購入した相続人がおり、相続人間で不公平が生じているというケースが考えられます。
もちろん、その購入価額が適切な金額であれば問題ありませんが、著しく廉価な場合、購入した相続人を不当に利する結果になってしまいます。
-
対処方法
「不相当な対価をもってした有償行為」は、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの」に限り、贈与とみなすことができます。
「不相当な対価」かどうかは、市場価額との比較によりますが、例えば、4000万円の価値のある不動産を、500万円ほどで売却していた場合には「不相当」と認められる可能性が高いでしょう。
贈与とみなされれば、不動産の価値に相当する4000万円を遺留分算定の基礎財産に加えることになります。
ただし、購入者に不利益にならないよう、遺留分権利者は、購入者に対して500万円をその対価として償還しなければなりません。
遺留分まとめ
遺留分とは、残された家族の財産を守るために法律で認められたものであり、極めて重要な権利です。
しかし、遺留分は、その行使方法や評価方法が複雑であり、専門的な知識を多数要します。
請求する期間も限られていますのでから、お早目に弁護士に相談するなどして対処した方が良いでしょう。
おすすめの記事
 遺産・相続遺産・相続問題は、昨今の高齢化社会の中、年々増加しています。
もっとも、遺産・相続問題は、…
遺産・相続遺産・相続問題は、昨今の高齢化社会の中、年々増加しています。
もっとも、遺産・相続問題は、… 遺言遺言は、一般的には「ゆいごん」と言われることが多いのですが、法律的には「いごん」と言います…
遺言遺言は、一般的には「ゆいごん」と言われることが多いのですが、法律的には「いごん」と言います… 遺留分遺留分は、請求できる期間に制限があるなど、その行使方法や評価方法などが複雑です。
そのため…
遺留分遺留分は、請求できる期間に制限があるなど、その行使方法や評価方法などが複雑です。
そのため… 相続税相続においては、遺産の分配方法だけでなく、相続税という税金の問題も生じます。
確かに、相続…
相続税相続においては、遺産の分配方法だけでなく、相続税という税金の問題も生じます。
確かに、相続… 交通事故交通事故とは、何の前触れもなく、突然起きてしまいます。
しかし、被害に遭われる方のほとんど…
交通事故交通事故とは、何の前触れもなく、突然起きてしまいます。
しかし、被害に遭われる方のほとんど… 後遺障害交通事故によって傷害を受けた際、治療を継続しても完全に完治せず、後遺障害が残ってしまうこと…
後遺障害交通事故によって傷害を受けた際、治療を継続しても完全に完治せず、後遺障害が残ってしまうこと… 休業損害(休業補償)交通事故に遭うと、治療費だけではなく、治療を行うための病院への入通院により、仕事を休まざる…
休業損害(休業補償)交通事故に遭うと、治療費だけではなく、治療を行うための病院への入通院により、仕事を休まざる… 熟年離婚「熟年離婚」とは、一般的には長く連れ添った夫婦が離婚することを言います。
昨今においては、…
熟年離婚「熟年離婚」とは、一般的には長く連れ添った夫婦が離婚することを言います。
昨今においては、… 不倫・浮気による慰謝料離婚・男女問題では、配偶者の不倫・浮気を理由として、慰謝料を請求したいというご相談が最も多…
不倫・浮気による慰謝料離婚・男女問題では、配偶者の不倫・浮気を理由として、慰謝料を請求したいというご相談が最も多…